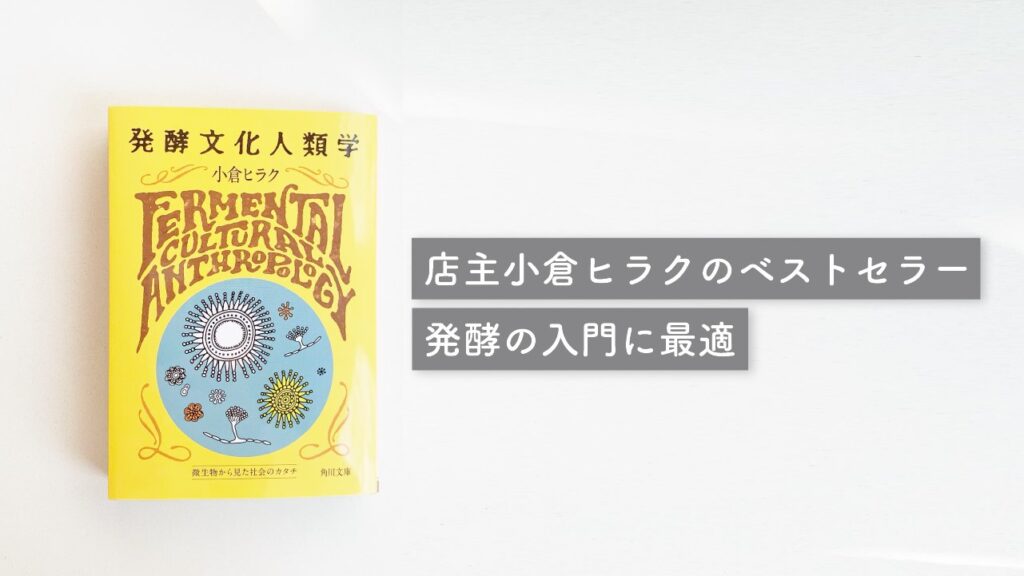小倉ヒラク
発酵デザイナー
Hiraku Ogura
第10回のゲストは、「発酵」にまつわる食文化に魅了され、日本各地の発酵文化をめぐって全国の醸造家と様々な活動を展開するなど、発酵業界に新風を巻き起こしている小倉ヒラクさんです。日本の食文化の重要な一角を担う発酵食と海との関わりや、これからの可能性についてお聞きしました。
プロフィール
1983年東京生まれ。「見えない菌の働きを、デザインを通して見えるようにする」ことを目指し、東京農業大学醸造学科研究生として発酵を学びつつ、全国の醸造家や研究者たちと発酵・微生物をテーマにしたプロジェクトを展開。アニメ「手前みそのうた」でグッドデザイン賞2014授賞。著書に『発酵文化人類学』(木楽舎刊/2017年)、『日本発酵紀行』(d47 MUSEUM/2019 年)。大学で発酵学の講師を務めるほか、海外でも活動。2019年、渋谷ヒカリエで発酵ツーリズム展を開催。2020年4月には下北沢に『発酵デパートメント』ショップをオープン。
・発酵に魅せられて、発酵をデザインする仕事を
・日本人にとって重要な「海の発酵」を忘れるべからず
・発酵食文化は「記憶の箱舟」だ!
編集部
「発酵デザイナー」という肩書きは、小倉さんが名付けたんですよね。どんなお仕事でしょうか?
小倉さん(以下敬称略)
はい。発酵デザイナーという仕事は、「目に見えない微生物の働きをデザインを使って見えるようにし、その価値を社会に実装する仕事」だと定義づけています。
編集部
「社会に実装する」まで含んでいるんですね。
小倉
初めは「見えるようにする」だけだったんですが、最近は社会への実装作業もしているなと気づいて、新たに付け加えました。2020年4月に下北沢にオープンした店舗「発酵デパートメント」や、発酵文化から日本の地方都市の多様性をひもとく「発酵ツーリズム展」など、発酵という文化をデザインで伝えるだけじゃなくて、文化や技術を継承していけるような社会的な仕組みづくりにも、ここ5年ほど取り組んでいます。醸造業界の未来に本気でコミットしたいという思いからです。
編集部
最初は「デザイナー」としてキャリアを積んでいらっしゃったとお聴きしましたが、発酵との出会いは?
小倉
20代半ばの頃、デザイナーとして忙しく働いているうちに体調を崩してしまって。そんな時に出会った発酵学者の小泉武夫さんに発酵食を食べることを勧められて、実際に食べてみるとだんだんと身体が元気になっていって、発酵の持つ力を実感したんです。その後、ご縁があって味噌づくりをしている会社のWEBデザインをしたら評判になり、そこから様々な醸造家さんから仕事を依頼されるようになって、発酵に関わるデザインの専門家のようになっていきました。「発酵と微生物に関わる仕事しかやりません!」と宣言したのは2014年で、その後、東京農業大学醸造科で学び、より本格的に関わるようになりました。いまは山梨に移住して、微生物とともに暮らす生活をしています。
編集部
本当に「発酵」に魅せられているんですね。日々どんなことを考えているんですか?
小倉
各地の発酵文化と向き合っていると、自ずと「日本とは、日本人とは何だろう?」という問いが浮かんできます。それくらい発酵っていう文化はその土地の気候風土や生態系、長い歴史と直結しているんです。この文化がどのように生まれて、どのように次の世代へ受け継がれていくのか知りたいと思うようになったんです。
日本全国を巡って調査をする中で、日本の発酵文化は「環境の過酷さ」の象徴だと感じました。自然環境の不安定さや厳しさ、また仏教による肉食の禁止など、厳しい環境の中で人々が何とか生き延びようと工夫しあった末に、発酵の文化が発展していった。食べ物がいつでも手に入る状態であれば工夫しませんからね。日本の発酵文化は人々の「知恵の豊かさ」の象徴でもあります。

たとえば秋田には「しょっつる」という魚醤がありますが、その原料であるハタハタという魚は漢字で「鰰」と書きます。どうして魚偏に神って書くんだろうと調べていくと、その土地の生態系や信仰などが関係していることに気づくんです。調べはじめると止まらなくなります!
編集部
ご著書の中では、「発酵と海の関係」についても書かれていますね。
小倉
僕は日本の発酵文化を、「海の発酵、山の発酵、街の発酵、島の発酵」と、4つに分類しています。「海の発酵」は、短い漁期に大量にとれる海の幸を有効利用するため。「山の発酵」は海とちがって、塩をふんだんに使えないので、酒粕や乳酸菌などを使うことが多いんですね。その土地でとれる旬のものを使うという点で、海と山は似ています。「街の発酵」と「島の発酵」はイメージしにくいかもしれません。保存ができて遠くへ運ぶことができる点で、中世から近代の経済のカギをになってきました。街を形成する事業の根幹に発酵があったという意味で「街の発酵」と呼んでいます。「島の発酵」は、海に囲まれた土地で水源もなく稲作も難しい、そんな厳しい環境の中で生きていくために、離島独自の発酵文化があることから名付けました。
さらに、発酵食品を食材で分類してみても、麹と並んで主役になるのが「魚介の発酵」。古代より仏教を国教として取り入れて以降、日本人は肉食を禁じられたので、動物性タンパク質の摂取を魚介に頼らざるを得なかった。そのことによって日本では様々な魚介の発酵食品が生み出されたんです。それくらい「海」というのは日本の発酵文化にとって大きな存在なんですよね。
編集部
腐りやすいという魚の性質は発酵と相性がよさそうですね。
小倉
そうですね。魚介類の発酵と稲作の相性もとてもいいんです。たとえば、「なれずし」という料理がありますが、これは魚の内臓などを抜いて米と一緒に乳酸発酵させることで、臭みのない状態で食べることができる保存食。山間地や冬の間のタンパク質摂取のために生み出された独特の文化です。鮒とか鮎など、その地域で獲れる魚を使います。見た目はアレですが、美味しいですよ!
 参考「なれずし」
小倉
それから、魚介の発酵食品として忘れてならないのは「魚醤」ですね。先に挙げた秋田のしょっつるもそうですし、能登にはカタクチイワシで作られる「魚汁(いしる)」という魚醤があります。タイにはナンプラー、ベトナムにはニョクマムという魚醤がありますが、それらとはまた風味が違う。その風味の違いがどこから来るのかというと、やはり土地それぞれの気候風土なんです。熱帯・亜熱帯気候である東南アジアでは、気温が高いので発酵速度が早くて、3カ月で発酵するものもあります。反対に能登では、比較的気温が低いため、ゆっくりと発酵が進むんです。冬を2回越させたりする。そうすると穏やかな風味のものが出来上がります。その土地の気候風土が発酵食品の味に大きく関係しているんです。
編集部
気候や風土によって味が変わるんですね。となると、地球環境が変化すると、その土地で作れるものが作れなくなったり、変化したりということもありそうですね。
小倉
それは大いにありますね。昔獲れていた魚介類が獲れなくなったということもあります。
宮城県気仙沼に「あざら」という郷土食があるんですが、これは「メヌケ」という深海魚のアラと、発酵が進んで酸っぱくなってしまった白菜の古漬けを、同じく古くなって茶色くなった酒粕で煮るという料理です。普通には食べにくいものを3つ掛け合わせると、和製ブイヤベースと呼びたくなるような美味しい料理ができてしまうのです。厳しい環境の中で、食べられるものを何一つ無駄にしたくないという地元の漁師の強い意思が感じられる郷土料理です。ただ、2011年の震災以降、気仙沼ではメヌケの水揚げが減ってしまって、あざらを作る人も激減。このままではあざらが途絶えてしまうと危機感を持った飲食店の店主が、気仙沼のお母さんに作り方を習って、メヌケをタラに変えてお店のメニューとして提供しはじめました。
参考「なれずし」
小倉
それから、魚介の発酵食品として忘れてならないのは「魚醤」ですね。先に挙げた秋田のしょっつるもそうですし、能登にはカタクチイワシで作られる「魚汁(いしる)」という魚醤があります。タイにはナンプラー、ベトナムにはニョクマムという魚醤がありますが、それらとはまた風味が違う。その風味の違いがどこから来るのかというと、やはり土地それぞれの気候風土なんです。熱帯・亜熱帯気候である東南アジアでは、気温が高いので発酵速度が早くて、3カ月で発酵するものもあります。反対に能登では、比較的気温が低いため、ゆっくりと発酵が進むんです。冬を2回越させたりする。そうすると穏やかな風味のものが出来上がります。その土地の気候風土が発酵食品の味に大きく関係しているんです。
編集部
気候や風土によって味が変わるんですね。となると、地球環境が変化すると、その土地で作れるものが作れなくなったり、変化したりということもありそうですね。
小倉
それは大いにありますね。昔獲れていた魚介類が獲れなくなったということもあります。
宮城県気仙沼に「あざら」という郷土食があるんですが、これは「メヌケ」という深海魚のアラと、発酵が進んで酸っぱくなってしまった白菜の古漬けを、同じく古くなって茶色くなった酒粕で煮るという料理です。普通には食べにくいものを3つ掛け合わせると、和製ブイヤベースと呼びたくなるような美味しい料理ができてしまうのです。厳しい環境の中で、食べられるものを何一つ無駄にしたくないという地元の漁師の強い意思が感じられる郷土料理です。ただ、2011年の震災以降、気仙沼ではメヌケの水揚げが減ってしまって、あざらを作る人も激減。このままではあざらが途絶えてしまうと危機感を持った飲食店の店主が、気仙沼のお母さんに作り方を習って、メヌケをタラに変えてお店のメニューとして提供しはじめました。
 小倉ヒラクさん提供 「あざら」
小倉
僕も実際、お店に行って食べたのですが、味噌や醤油を使わず、漬物の酸味と酒粕の旨味で味付けがされていて、食べやすく美味しかった。ペアリングでワインをおすすめしてもらいましたが、ぴったりでしたよ!
店主の方にお話を聴く中で、「メヌケにこだわっていると、あざら自体が作れなくなってしまって滅びてしまうかもしれない。そもそも、あざらは普通に食べたら美味しくないものを組み合わせて美味しいものをつくる料理。大事なのは『どうつくるか』ではなく、『どうしてつくったか』だと思う」と話されていて、僕は深い感銘を受けました。
編集部
同じ材料で同じ製法でつくることにこだわると、逆に続けられなくなるんですね。
小倉
そうです。伝統の本質を「様式」ではなくて「発想」だと捉えて、現代の環境に合わせてリデザインする。発酵食品の本質である「ない」状態を「あるようにする」意思を汲み取ったタラのあざらを味わって、僕は発酵文化の未来を決めるのは時代の流れじゃなくて、個人の創造性にかかっているなと思いました。かつての役割を終えたなら、新しい役割を発明すればいいんです。
編集部
なるほど。新しい役割ですか。冷蔵庫ができたから、保存食はもう必要ない、と必要性だけで切り捨てるのでなくて、昔の人の叡智を受け取って未来にどうつなげていくか、ということですね。
編集部
それでは最後の質問です。小倉さんが考える、現代社会において発酵文化が担う役割とはどんなものでしょうか。
小倉
1000年以上の歴史を持つ日本の発酵文化は、非常にサスティナブルな文化。現代に生きる僕たちにもヒントになるテクノロジーも詰まっています。そういう有用なものが、私たちの足元に存在している。産業規模も大きくて、海外からも注目されている。伝統文化だけではありません。明治以降にも、日本は微生物の分野でいくつもイノベーションを生み出し続けている。発酵は日本においてバイオテクノロジーとしても非常に伝統があります。そういった発酵の持つポテンシャルが今まであまり語られてこなかったんですよね。長い年月をかけて培ってきた発酵文化は、その国の礎になる部分だと僕は考えています。
海に囲まれ、海の恵みによって生かされてきた日本人がどのように食に向き合い、その土地の中でどう生き延びてきたのか、発酵はそのことを現代に伝える「記憶の箱舟」のようなもの。そういうものを大事にしないと、国の未来はないよ、くらいに思います。
小倉
地地球環境レベルでも国の経済戦略レベルでも、成長主義の限界というものを人々は感じているように思います。そんな中で、競争っていう土台の上にない発酵の文化は、私たちの希望になると思うんです。もう少し具体的にいうと、発酵とは、見えない自然をとらえ、ミクロの生物と関係を結び、生み出された価値を楽しみ分かち合う心がある、そのことを発酵文化と呼んでいるんですよね。あえて「希望」という言葉を使いますが、そういうニュアンスが皆さんに伝わったらいいなと思いながら、僕は活動しています。
小倉ヒラクさん提供 「あざら」
小倉
僕も実際、お店に行って食べたのですが、味噌や醤油を使わず、漬物の酸味と酒粕の旨味で味付けがされていて、食べやすく美味しかった。ペアリングでワインをおすすめしてもらいましたが、ぴったりでしたよ!
店主の方にお話を聴く中で、「メヌケにこだわっていると、あざら自体が作れなくなってしまって滅びてしまうかもしれない。そもそも、あざらは普通に食べたら美味しくないものを組み合わせて美味しいものをつくる料理。大事なのは『どうつくるか』ではなく、『どうしてつくったか』だと思う」と話されていて、僕は深い感銘を受けました。
編集部
同じ材料で同じ製法でつくることにこだわると、逆に続けられなくなるんですね。
小倉
そうです。伝統の本質を「様式」ではなくて「発想」だと捉えて、現代の環境に合わせてリデザインする。発酵食品の本質である「ない」状態を「あるようにする」意思を汲み取ったタラのあざらを味わって、僕は発酵文化の未来を決めるのは時代の流れじゃなくて、個人の創造性にかかっているなと思いました。かつての役割を終えたなら、新しい役割を発明すればいいんです。
編集部
なるほど。新しい役割ですか。冷蔵庫ができたから、保存食はもう必要ない、と必要性だけで切り捨てるのでなくて、昔の人の叡智を受け取って未来にどうつなげていくか、ということですね。
編集部
それでは最後の質問です。小倉さんが考える、現代社会において発酵文化が担う役割とはどんなものでしょうか。
小倉
1000年以上の歴史を持つ日本の発酵文化は、非常にサスティナブルな文化。現代に生きる僕たちにもヒントになるテクノロジーも詰まっています。そういう有用なものが、私たちの足元に存在している。産業規模も大きくて、海外からも注目されている。伝統文化だけではありません。明治以降にも、日本は微生物の分野でいくつもイノベーションを生み出し続けている。発酵は日本においてバイオテクノロジーとしても非常に伝統があります。そういった発酵の持つポテンシャルが今まであまり語られてこなかったんですよね。長い年月をかけて培ってきた発酵文化は、その国の礎になる部分だと僕は考えています。
海に囲まれ、海の恵みによって生かされてきた日本人がどのように食に向き合い、その土地の中でどう生き延びてきたのか、発酵はそのことを現代に伝える「記憶の箱舟」のようなもの。そういうものを大事にしないと、国の未来はないよ、くらいに思います。
小倉
地地球環境レベルでも国の経済戦略レベルでも、成長主義の限界というものを人々は感じているように思います。そんな中で、競争っていう土台の上にない発酵の文化は、私たちの希望になると思うんです。もう少し具体的にいうと、発酵とは、見えない自然をとらえ、ミクロの生物と関係を結び、生み出された価値を楽しみ分かち合う心がある、そのことを発酵文化と呼んでいるんですよね。あえて「希望」という言葉を使いますが、そういうニュアンスが皆さんに伝わったらいいなと思いながら、僕は活動しています。
 編集部
今回の「発酵」という切り口から、「海」がとても密接につながることがわかって嬉しくなりました。海に囲まれたこの国で、先人たちが生き延びるための知恵を自然と受け継いでいるんだなと。
人間にとって都合のいい社会の追求だけでなく、微生物も含めた多様で複雑な自然と共生している、発酵文化からそんな価値観をもった人とのつながりを想起しました。小倉さんのおっしゃる「希望」というニュアンスが少し分かったように思います。
発酵食品って体にもいいですし。これからもっと興味を持つ人が増えそうです。さらに「発酵」を入口にして、海の未来に興味を持つ人が増えてくるといいと思いました。ありがとうございました!
編集部
今回の「発酵」という切り口から、「海」がとても密接につながることがわかって嬉しくなりました。海に囲まれたこの国で、先人たちが生き延びるための知恵を自然と受け継いでいるんだなと。
人間にとって都合のいい社会の追求だけでなく、微生物も含めた多様で複雑な自然と共生している、発酵文化からそんな価値観をもった人とのつながりを想起しました。小倉さんのおっしゃる「希望」というニュアンスが少し分かったように思います。
発酵食品って体にもいいですし。これからもっと興味を持つ人が増えそうです。さらに「発酵」を入口にして、海の未来に興味を持つ人が増えてくるといいと思いました。ありがとうございました!
インタビュー&Text/児浦 美和 Photo/Pecogram